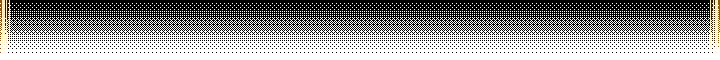『今年から、球技大会を年2度行うこととする』
何気なく発表されたこの通達が、争乱の始まりだった。
「おい。聞いたか?」
「ああ、冬季球技大会だってな」
「誰だよ?! そんな酔狂なもの考えた奴は!」
学生達は通達の張り出された掲示板の前で、口々に勝手なことを言い合う。
「特に深い意味はありませんよ。単純に冬の間は娯楽も運動量も減りますから、その解消が目的です」
双樹会会長、マイヤは今回の発表に関して笑顔でそう説明した。本当にそれだけなのか誰もが尋ねようとしたその時、マイヤは言葉を続ける。
「ただ、この冬季球技大会を決めるに当たって、ある人物の尽力があったのは確かです」
「ある人物……って?」
口々に尋ねる生徒達に、マイヤはこう言った。
「それは本人との約束で、秘密ですよ」
冬季球技大会の準備が着々と進められる中、学生達の間に再び驚きの声が挙がった。
「よりによって、これかよ……」
そう言う学生達の目の前には、球技大会の種目が書かれた通達が張られている。
その種目とは、『トリムラリー』と呼ばれるものだった。
「ねぇ、マリー。トリムラリーって何?」
蒸気研に遊びに来ていたレダは、マリーに尋ねる。すると、マリーはこう答えた。
「えっと、トリムラリーって言うのは……。ちょっと待って。辞書を引いてあげるわ」
そして、近くにあった辞書を開く。程なく、マリーは顔を上げ、レダに改めて説明を始めた。
「辞書によると、『2チームがネットを境にコートの左右に分かれ、ボールを手で相手コートに打ち込み、得点を競う競技。1チームは2人』って書いてあるけど……わかる?」
マリーの問いに、首を振るレダ。マリーも困り顔だ。
「要は、2人でボールをこうやって『トス!』とか『レシーブ!』とか、『アターック!』とかやって、3回ボール触る間に、相手の陣地に落とす球技……なんだけど」
マリーは身振り手振りで説明を続ける。その熱意が通じたのか、レダはようやくトリムラリーのなんたるかを理解したようだ。
「ボクも出たい〜。アルファントゥと一緒にあたーっく! にゅふふ」
レダがそう言って、右手でボールをはたき落とす真似をする。が、マリーは首を振った。
「リエラはダメだよ。誰か、フューリアのパートナーを見つけないと」
その言葉に、レダがぷうと頬を膨らませながら文句をつける。
「けち〜。じゃあ、ボク、マリーと一緒に出る〜」
「あ、わたしはダメ。当日は、蒸気式演算回路組込型自動得点掲示板『エクストリームカウンター』のメンテナンス担当なのよ。誰か代わってくれれば、出られるんだけど……」
その言葉に、レダは珍しくきりりとした表情で言った。
「じゃあ、ボク、ぱーとなーをさがす〜! マリーの代わりの人も、さがしてあげるよ!」
更に時は進み、日程・賞品などが次々と決まっていった。
「ねぇねぇ。キックス〜。冬季球技大会の賞品、聞いた?」
天文学部へ向かう途中のキックスを呼び止めてそう言うのは、ネイ。
「知らねぇよ。興味ないし」
そう言って階段を上ろうとするキックスのズボンを、ネイが掴む。
「待ってよ〜。賞品、あのハイトマーのウィニングボールだよ! もちろんサイン入りで、お宝ものなんだから〜」
ハイトマーとは、プロのトリムラリー選手である。コートを縦横無尽に動き回り、どこからでもアタックを打ち込む彼は、“白い弾丸”と呼ばれて恐れられたと言う。惜しまれながらも引退したが、その人気は今も高い。
「特に、高位置からの高速アタック『メテオソード』は、天下無双の破壊力で……って、キックスぅ?!」
ネイが語っている間に、キックスは階段を上りきっていた。階段の下に一人取り残されたネイが、慌ててその後を追いかけようとした時。
「相変わらずですこと! ネーティアさん」
妙に高飛車な声が、時計塔広場にまで響き渡った。ネイが振り返ると、そこには奇妙な形に頭を結った一人の少女が、高笑いしながら立っている。
ネイは恐る恐る、彼女に尋ねた。
「失礼ですが……どちら様ですか?」
彼女は一瞬呆然としたが、すぐに気を取り直してネイを指さした。
「このリッチェルを、忘れたとは言わせませんことよ?」
「あー! もしかして、“自滅姫”リッチェル?」
ネイはそう言いながら、リッチェルへと指さし返す。リッチェルはその指を手で払いながら、ネイの元へと近づいた。
「その二つ名は言わないで欲しいですわね。そもそも、その二つ名を付けられたのは、あなたのせいですのよ?」
「そんな過去のことは、お互いに水に流さない?」
「今更、そんなことは言わせませんことよ!」
衆人環視の中で言い争うネイとリッチェル。どうやら、この2人。何やら訳ありのようだ。
2人は額をつき合わせ、舌戦で火花を散らす。そして、リッチェルが再びネイを指さした。
「勝負ですわ! 今度の冬季球技大会で、決着をつけませんこと?」
すると、自信たっぷりの顔でネイも頷く。
「いいわよ。受けたげる。けど、『学園最強タッグ』と謳われた、私とキックスに勝てる?」
「自称の学園最強に負ける気は、更々ありませんことよ! 最強のパートナーを見つけて、その鼻をあかしてあげますわ」
リッチェルも自信たっぷりの顔でそう言い捨てると、踵を返して学園へと向かっていく。ネイもリッチェルに背を向け、天文学部への階段を駆け上った。
「キックス〜! いっしょに冬季球技大会に出て〜!」
「そうか。ハイトマーのウィニングボールか」
冬季球技大会の賞品を従者から聞いて、ランカークはしばし考える。だが、従者からしてみれば、次に彼が言う言葉は明らかだった。
「一流選手の物は、高貴なる者にこそ相応しい。これがどういう事か、わかるな?」
ランカークの言葉に、従者は頷く。
当然だが、ランカーク自身は球技大会などに出る気はない。金を積めば、協力者は現れるからだ。もっとも、最悪の場合は、従者自らが大会に出なければならなくなるだろうが。
「では、良い結果が聞けるのを待つことにしよう」
ランカークがそう言うと、従者は行動を開始した。
その後、学生達の間に「ウィニングボールをランカークに渡すと、報酬が出る」との噂が流れたのは、言うまでもない。
そして、参加申し込みの日が訪れる。
注目のネイ・キックス組は早々に受付を済ませて、申し込み会場入り口で他の参加者達の様子を見ていた。
「この面子なら、優勝はいただきなのです」
ネイはそう呟いた。 |
|