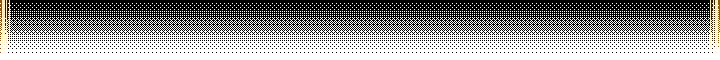深淵に潜むものが何であるのかを語るためには、深淵とは何かを語らなくてはならないだろう。
深淵――異界。神々の座す場所。すべての超常の力の源。
リエラの生まれし場所。リエラの還る場所。
――人が死して還る場所。……人が生み出した場所。
そこでは人の羽ばたく想いが形を創る。人の熱い願いが力になる。人の深き慈愛が調和をもたらし。それらの粘り強い積み重ねが安定をもたらす。
そうして深淵は生まれた。そうして深淵に棲むものは生まれた。
深淵に潜む怪異もまた、その落とし子ならば。
それは人の――が産み落とした化け物なのか――
まだ学園にフランの姿はない。フラウニー・エルメェスの呪われた運命は知る人ぞ知るところとなっていたが、しかし万人がそれを知るというほどのこともなく、またアルメイスは日常のような顔を見せていた。
最近あった目立つ異変を言うならば、ショーゼル街の辺りの住人が、その地区がテロリストに狙われているということで避難したことだろう。いまだに避難した者たちは自宅には帰っていない。
元々アルメイスは学園都市を機能させるためだけの住人しかいない。学生でなかったならば、仕事で移住してきたか、研究生として卒業生が居残っているか、講師教授の類かに大別される。なのでアルメイスにしか行き場のない者というのは、通常はあまりいないのである。
どうしてもアルメイスにいなくてはならない者については、寮の空き部屋で事足りた。通商や業務でアルメイスに滞在していた者ならば、いくばくかの保証金を手にして元々の故郷へ里帰りの休暇に変えてしまった者が多かった。だから、それらもまだあまり深刻な課題になることなく、今に至っている。当事者たちは、原因となったレアン・クルセアードの回復によって解決されるものと思っていたようだ。
実際には、その鍵を握っているのはレアンではなく、今もまたランカークの屋敷に身を寄せているフランであるわけだったが。
「どうなんだ……あの……娘は」
サウルが食事を運んできたとき、レアンがふと訊ねてきて、白い林檎の皮を剥きながらサウルは顔を上げた。
「レディフランなら……まあ、普通に戻るっていうのは、無理だろうね。隠れている間は薬を使って眠らないでいたようだけど」
薬という言葉に、レアンは顔を顰める。先日わずかに顔を合わせたときに、そうではないかとは思っていたが……しかし、体や心に負担をかける薬はレアンにとっては鬼門だ。
「もちろん今は使ってないけど……残っちゃうこともあるしね。実際、やっぱり今もあんまり寝てないらしいよ」
眠らないのではなく、眠れないという意味で。不安がフランを苛んでいるのだろう。また眠りのためにイルズマリを犠牲にしたことを、心晴れやかには受け止められるまい。だが、イルズマリが戻ってきたなら……再び、繰り返しになるのだ。
イルズマリは戻ってくるだろう。そんな記述がわずかでも残っているということは、過去にそうしたことがあるということだ。元来エルメェス家の呪いのことを知る者の間でも、その記述についてが廃れていったということは、それには限定的な効力しかないということだ。何よりイルズマリがフランのそばにいたということが、イルズマリが戻ってくる証拠である。
「彼女を救う方法は、正直、僕にはわからないけど。何か確実な方法があれば、過去にすでに行われていただろうし」
呪いの歴史は長いので、皇室に属し帝国の情報を握る職に就くサウルは、その呪いの存在自体は初めから知っていた。だが、解決の方法は知らない。それはまだ誰も知らぬことなのだろう。
それはいつ降臨するかもわからぬ、深淵より来る者。それを消滅させる方法はないのだろう……人がこの世にある限り。リエラがただ唯一の方法によってしか、消滅することのないように。それは自らにしか従わぬ、エゴイズムの具象神。
簡単で確実な解決の方法が、過去の記録に残されていることはありえない。何故なら、それを実行すれば解決するということがわかっているならば、今このときまで問題が残っていることはないからである。抜本的な解決があるとすれば、その道は過去の中ではなく、今を生きる者の創造する力の中にある……本当にあるか否かも約束はされない苦難の道であるが。
ともあれ、イルズマリが戻ってくるたびに殺される、殺されるために戻ってくる……なんて、そんなことには、やはりフランの心は耐えられるまい。そういうこともあって、代々多くの依り代は心を病んでいったのかもしれない。
後悔は多い。
それがやむをえないものであってもだ。
後悔の迷路は堂々巡りで、どこへ向かっても出口は見えない。
ただ、伝承に伝わることは、出現を抑える方法だけだ。
「ただまあ、出てこないようにする方法はあるみたいだけど……僕は知らなかったけどね」
その方法については、サウルは多くは語らなかった。自分が当事者ではないと思っているからかもしれない。いや、ルーの未来について無関係でないのならば、サウルも無関係ではないのであるが。
四大リエラの主のうち、大きく対立するのはルーとレアン。
誰が妥協し、どのような未来を目指すのか。少数派を力をもって屈服させても、調和したことにはならないだろう。それは心の問題なのだ。
すべてが丸く収まらないなら、やはり収まるところまで何かを切り捨てていくことになるのだろう。
そのとき切捨てられるのは、彼らかもしれない。サウルが切り捨てられるときには、レアンも共々だ。逆もまた真。
あるいは、彼らが切り捨てる側に回るのか。ルーを切り捨てるときには、エリスも共にかもしれない。あるいは更なる時間稼ぎに、やはりフランを切り捨てるのか。
レアンか、ルーか、フランか……
遠からず、誰かが誰かのために選ばなくてはならない時が来るかもしれない。すべての選択は『保留』だ。選ばぬままに先へ進められるのなら、それでも良いが……
「……俺は、妥協はできない」
ぼそりと、レアンは呟いた。
「ま、譲れないことは誰にでもあるね」
さらりと、サウルはそう答えた。
「当面、僕の希望は君に近い。だからもちろん、僕から君に妥協しろとは言わないよ。言ってくる者もいるだろうけどね……」
そこで、サウルは一度言葉を切った。
「本当に、君だけの、君たちだけの問題なのかな。君たちだけが、責任を負うことなのかな」
調和するべきは、四大リエラの主だけなのだろうかと。
つかみどころのない話のかたわらで、小さな願いが何もなかったわけではない。
「あのね……」
ラジェッタがアルメイスに来て、もう一年ほどになるだろうか。その言葉も、以前ほどにたどたどしくはない。
「おうちにかえろうとおもうの」
それはラシーネが言ったことに触発されたのだろうか。ラジェッタは、レイドベック公国に帰ると言い出した。
ラジェッタの故郷はレヴァンティアースとレイドベックの国境に近いとは言え、いまだ一触即発の敵国である。そこでは、フューリアの存在はそもそも許されない。自存型リエラを連れたラジェッタが、そこで暮らすことは不可能だ。
だが……
フランは今も、ランカークの屋敷に身を寄せていた。自分の家に帰らなかった理由は……人から身を守るためだろうか。地下から地上に出てきただけで、カレンの仕事はあまり変わり映えしないようだった。
フランと話をしたい者にとってはランカークはやや難関だが、無制限にフランに人が近づくことを抑制する関所にはなるだろうか。
フランの様子も、あまり眠っていないことに変わりはない。ただ薬を断ったというだけだ。
イルズマリ――アルディエルは帰ってくる。
だが、それはまだのようだった。
帰ってきたときには、繰り返される。
そのとき、どうするべきか……
そのときまでに、するべきことをしなくてはならない。
そして、そのときのための準備を怠るわけにはいかないだろう。
そのときまでに、選びきれなかったときのために。
エイムが消失した後、ラジェッタの元へリエラが帰還するまでにかかった時間は一週間足らず。それと同じ時間はもう過ぎた。何を決めるにも、時間はあまり残されてはいない……
それが多分、約束の時。
本当の選択の時。
ただ見守る者にとっても。
選ぼうとする者にとっても。
もう答は出ているのかもしれなかった。
まだ答は出ていないのかもしれなかった。
すべてにおいて――
揺らぐ未来を望む形に繋ぎとめるための、後一歩。
その一歩が――
明日を選ぶ。 |
|