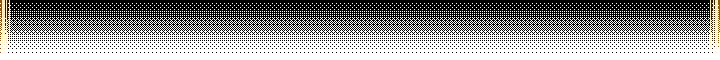レアン・クルセアード逮捕。それがアルメイスタイムズの一面を華々しく飾ることはなかった。ただ紙面の片隅に、テロリストの容疑者が一人身柄を確保されたと出ただけだ。その記事からは、その者がその後どうなったかは窺いしれない。
タイムズ社局長ロバート・ブルックリングにそのことについて聞いたなら、
「やってらんねえよ」
と、珍しく彼がくさっている様子が見られただろう。
圧力があったかなかったかというところには言及はしないが、なんらかの取引はあったようだった。ロバートはいずれの見返りにか、違うネタを手に入れたようだ。しかし、もちろんそのまま鵜呑みにして記事にするようなことはなかったが……記者としてのプライドによって。裏が取れるなら、ソースがどこであれスクープに違いないだろう。しかし、提供された情報とその入手経路のすべてが真実だったと仮定しても、それには少し時間がかかるだろうと思われた。
ロバートはどうするべきかと考えているようだった。レアンについて記事にすることも、まだ諦めきれてはいないようで。彼が捕まった夜に同時に起こっていた数々の出来事についても、まだこっそりと調べているらしい。
そう、それは現場にたくさんのアルメイスの学生がいたことや、その夜から行方の知れなくなった一人の女生徒のことについて。その夜まで続いていたリエラの力による破壊行為が、止んだことについて。
新聞はマスコミュニケーションである。真実を白日の下に曝すのに、効率的かつ効果的な媒体だと言えるだろう。
その真実の向こう側には……やはり転落が待っているのだろうか。
身柄を確保されたはずのレアンのいる部屋には、鍵はかかっていたが……それは外部からの侵入者からレアンを守るためだった。逆を言うならば、レアンの逃亡を阻止するための鍵はない。屋敷の主の言い分としては、「無駄だから」である。逃げられるほどに回復して、逃げるつもりならば、鍵があってもなくても変わらないというわけだ。レアンにどんな拘束も意味はない。それは事実だ。そして最も効果的であろうという方法が屋敷の主が丸一日見張っていることだというあたり、実に現実的でない。
限界まで傷つき消耗して身動き一つできないような有り様だったから、彼は捕まったのである。その後……あまりレアンは回復していない。レアンとしては帝国の手に落ちたという認識であり、食事もろくに取らないからだ。だが、そういう態度でも、彼が死ぬには普通の者よりも少し長くかかるらしい。アークシェイルの加護が、その死を緩慢なものにしているようだった。
屋敷の主としては、話を聞くなりするなりしたいようだが……レアンは今のところ、語ることはなく、聞く耳は持たぬという態度であるようだ。
そのままベッドの上で……ゆるゆると死に向かい、レアンにも疑問はあったようである。手をつけない食事も、欠かさず三食供される。しかも毎回、目の前で毒見して見せてまでだ。だが話を拒む中では、疑問を訊いて確かめることもできなかったのだろう。
そんな中で、いくらかの日が過ぎる。
「そろそろ、覚悟してくださいね」
レアンの枕元で、屋敷の主サウルが言った。
「そろそろ……来る。おわかりだろうと思うが、鍵も何も、彼女には意味がない。というか、多分、この屋敷の空間ごと吹き飛ばすと思う」
レアンが自ら死ににいくのを待ってくれるほどに寛容な人物ではないことを、サウルは知っているようだった。ならば運び出せば良いだろうとレアンは思う。その気持ちを読んだかのように、サウルは続けた。
「このままなら、あなたを荒野にでも放り出す以外に、被害を最小に抑える方法はありません。だが、僕の立場ではそれは無理だ。あなたを放逐するようなことは。それに、あなたが死ねば結局大きな被害に繋がる。それがわかっているから、僕はあなたと心中するか……あなたと協力するしかない」
協力という言葉に、レアンは胡散臭そうな表情を見せる。
「でも、あなたには協力する気はない……お手上げだ」
だからせめて覚悟を、ということのようだ。死にゆく者に覚悟というのも、おかしな話かもしれないが……少なくともサウルが、そして逃がさないのなら周辺の住民もレアンと共に心中することになる。その覚悟をという意味なのかもしれなかった。
「もう、残された時間は短い。あなたに会って話をしたい人は他にもいる。聞くかどうかはともかく、会うくらいはしてあげてほしいな。みんな、中途半端に関わって、気分がすっきりしないこともあると思うし。真っ最中に、一緒に吹き飛ばされないとも限らないが……」
会うときには自分が立会い、下手な手出しはさせないことを約束するともサウルは言った。
「あなたが望むなら、密談してくれてもいいけどね……」
「いかがいたしましょうか」
「どうにも……必ず、あそこに現れるわ。でも、どうにもならない。あの回りの住人を、避難させる言い訳を誰か考えてちょうだい」
学園長……ルーはこめかみを押さえながら……立ち上がる。きつく厳しい顔つきだ。マイヤはそれを視線で追った。
「私に現場を押さえられるならいいけれど……そうできるとは限らないわ。今、アークシェイルの力が媒介の弱化で限りなく弱まっている分……近くでないと、こちらの圧力も効き辛いのに」
ルーがずっとそこに居続けることは……現状ではできないだろう。そこは、サウルの屋敷なのだ。ルーにしてみれば、敵の手中に飛び込むも同然の行為。
「頼んだわよ。私も、気をつけておくけれど……」
ルーが頭を悩ましていることの一つには、クレアがレアンに会いたがっていることもあった。
カレンは、自分がどうするべきかを考えていた。
「……せめて食べない?」
そこは、もちろんランカークの屋敷だ。その地下で、最近のカレンはほとんどの時間をすごしていた。
そこにいるのは、主人であるランカークではない。地下室の片隅で、膝を抱えているのは……やつれ果てたフラウニー・エルメェスだ。
ランカークはフランを心配はしているけれど、フランが望まないので立ち入らないようにはしている。代わりに、カレンがフランの面倒を見ていた。
だから、フランがずっと眠っていないのをカレンは知っている。求められるままに、カレン自身が薬も調達してきたからだ。だが、もうフランが限界であることも知っている。
食事もしないで、眠りもしないで、人がもつはずがない。
この屋敷にフランを連れ込んだのが誰であるのか、カレンは知らなかったが……
見当はついていると思っていた。
どうするべきか、カレンは真剣に考えていた。 |
|