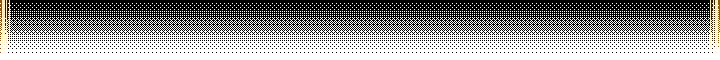雪は例年並にまで落ち着いていた。そこここに大雪の頃の雪掻きの名残を残してはいたし、完全に止んだわけでもなかったが。アルメイスの冬に雪がなければ、それも異常気象だ。
そんな、じきに年も書き換わろうという最後の月。金色の暴走リエラに紛れて、真夜中に静かに街を彷徨う影があった。
いや、彷徨っているのではない。彼女は、自分の望むものがどこにいるかを理解しているのだから。
微風通りの路地裏を。あるいは、アリーナの片隅に。
彼女は探し、彼女は追い、そして見つけ出しては狩り立てた。
多くの場合に誰もそれに気づかなかったのは、それは、人の生きる位相よりわずかにずれた場所での出来事だったからだ。どんなに破壊の力を撒き散らそうとも、人が眠る世界にそれが響くことはなかったからだった。
――そのときまでは。
「諦めるがよい。おぬしの位相がこれ以上にこちらに戻れば、もう逃げ切れまい」
「……余裕だな。俺が戻れれば、そんなにのうのうとはしてられまい?」
「その通りじゃ、アークシェイルの影よ。だから今しかないのじゃよ」
彼女の傍らにいた銀の鷹は輝きを増して、翼を広げる。
「おぬしが完全にアークシェイルの影響下から出る前に、消えてもらう」
人気のない修練場に、光が走った。もう、的となるアークシェイルの影……レアン・クルセアードの位相は限りなく現実の世界に近づいていたので、その光は現実にも漏れた。轟きと衝撃が。修練場の近傍に人家は少ないが、しかしそれは、その多くが飛び起きるに足るものだった。
「……俺に普通の攻撃は効かんと、いつになったらわかるんだ」
「細かいことを気にするでない。おぬしがおぬしである限り、消耗していけば、いつか効くであろ?」
「今は防御しきってるようだが、繰り返せば、おまえだって無傷ではすまなかろうに」
「心配してくれるのじゃな、すまぬの。じゃが、気遣いは無用じゃ……この体が消えても、次に宿るだけのことよ」
確かに、しばらくは動けぬがの……と、彼女は金の髪を揺らして優雅に微笑う。
「それでも、おぬしと共にアークシェイルを滅することが出来れば、わしと違ってアークシェイルの復活までには時間がかかる。おぬしには礼を言わねばなるまいよ。彼奴らを従えようとした者はおぬしが初めてじゃ」
今までは誰もが従属に甘んじておった……と。
そんな会話も、誰知る者なき、時と世界に飲まれる記録。
そして、再び光が轟いた。
いくつかの光の後に、残されたのは、ようやく世界に現出した破壊の爪痕だけだ。
そこで何が起こったのかを、そこからだけで推測出来る者は少なかった。
フランは急速に、日に日にやつれていくように思われた。
「エリスさん」
フランが頼った者は、そう多くはなかった。おそらくは、どんな方法を取っても自分を止められると思った者に。あるいは……
「お願いがあるんです」
逆にフランは、自分に親しい者には、けして言わなかった。
そして何にせよ、誰にも同じ願いを口にした。
それでもその詳しくを、語ることはなかったが……
「……レアンさんを助けてくださいませんか」
現世に戻ろうとする彼を狙う者の手から……と。
「どうなさるおつもりなのですか? 私はしばらく姿を隠しても構いませんでしたし、捕まっても……」
青年の声には責める響きがあった。
「なるようになるよ。まあ、約束はしてきたからね。今後は、会長を交えてのみ話をすると」
サウルはその責めをかわすように、肩をすくめる。
「応じますか? マイヤーが。お言葉ですが、私でしたら……」
「でも、彼は今、アルメイスの双樹会の会長だからね。学生たちの願いに応じないなら、応じないなりの対応がいるだろう?」
「本当にマイヤーが一緒でなければ、誰とも話をしないおつもりで?」
「挨拶くらいはするよ。人の話も聞かないと言っているわけじゃない。でも、質問には答えない……そういう約束だから、特別な人は作らないよ。誰の質問にも、彼の立会いのもとでしか答えない。だが、どんな質問にも、彼の前でなら答えよう。僕の知る限り」
サウルの屋敷で、居間にいる人影は一つだ。サウルのものだけ。
青年は声だけの存在だった。
どこから喋っているのか、その場にいても判断はつきにくい。
「それは諸刃の剣です、サウル様。それでも、あちらが動きだすとは限りません。ここまでも、十分に慎重でしたから。動かなければ……本当なのでしょうか、姫がラウラ・ア・イスファル計画を利用して帝国の転覆を狙っているなど。もし違っていたら」
疑問を吐露する声に、サウルは苦笑いを浮かべる。
「さてねぇ……でも、別に、違っていて困ることなんかないだろう? 間違いだった、それだけだ。間違っていたって、誰も困りはしない。帝国転覆のために誰も犠牲になることはなく、そのための戦いも起こらないだろう。それが明らかになるだけだ、良いことじゃないか」
「……私にはわかりません、姫が帝位を欲っしているのならば……」
「多分、欲しいのは単純に帝位じゃないんだと思うなぁ」
声は沈黙した。
違っていたときには彼の主の身が困ったことになることも、当たっていたとしても無事ではすまないかもしれないことも、わかっていたからだろう。
「申し訳ありません」
「あなたが謝ることではないわ……でも、あの人は気が付いていると思うべきかもしれないわね」
「どこまで……」
「わからないわ」
学園長は考え込んだ。
「とにかく、ボロを出さないように気をつけて」
それでも、答は出ない。だから、そう注意する以外にはなかった。
「肝に銘じておきます」
ふう、と学園長は息を吐く。
「厄介ごとは続くわね」
「……はい。修練場の破壊の件ですが」
マイヤは気を取り直して、報告に入る。
「破壊跡から調査するかぎり、殿下の危惧された通り、おそらくアークシェイルが関わっていることは間違いありません」
「でしょうね……レアンの自我が復帰して、破壊活動に入ったのかしら?」
「能動的な破壊活動の可能性よりも、防御能力の発動の結果の可能性が高いように思われます」
「誰かが、ちょっかいを出したということね? でも、死体は転がっていなかったし、該当する怪我人もいないわ」
「はい」
「……本当に続くわね」
更に深く溜息をつき、学園長はマイヤに命じた。
「とりあえず、様子を見ていて。どうしたものかしらね……出来れば、巡回に学生を回したいけれど、危険だし。私も注意して見に行っておくわ。クレアはまだ諦めてないから、あの子が巻き込まれないようにしないと」
「しかし知って……いるのでしょう? なのに何故」
「……わからないわ、私には」
ラウラ・ア・イスファル探しは、全体を見れば下火になりつつあった。ラジェッタと共に探していた者たちの動きは表立って見られなくなったためだ。
だがクレアとランカークは、まだラウラ・ア・イスファルを、力を求めている。ランカークはそろそろ飽きてきていたが、フランの手前退けないようだった。だが型通りの噂以上のものを知らず、行く先も見当たらない。
クレアのほうはと言えば、噂の意味にも気付いているのかもしれなかったが……それでも、動きまわることをやめない。
そしてラジェッタは……
「おとうさん」
違うことを考え始めていたようだった。
「おじちゃんは、だれとけんかしてるの?」
父親はその問いには答えなかった。それを説明するのは難しかったからだろうか。
「ね……なかなおり、できない?」
もしかしたら、ラジェッタはわかっていると思ったからかもしれない。
「できるかな……おじちゃんは、とても怒っているから……許してくれないかもしれないし」
やっと……エイムは静かに答える。
「それに始まりは、おじちゃんが悪かったわけじゃないけれど……悪いことは悪いことだと言われるかもしれない」
「なかなおり、できない? ごめんなさいっていってもだめ? だれにごめんなさいっていえばいいの? だれがごめんなさいっていえばいいの?」
ラジェッタには、やっぱり難しい話だろうか。
「おとうさん、しらない? おにいちゃんたちならしってる? だれにきいたらいいの?」
「……仲直り、できるといいね……」
けれどだからこそ、思えることもあるのかもしれなかった。
そんな年末が近づいたある夜。街の一角が光と衝撃に吹き飛ばされた。
それによっていくらかの建物が崩れ……いくらかの罪なき犠牲者が出ることとなった。 |
|