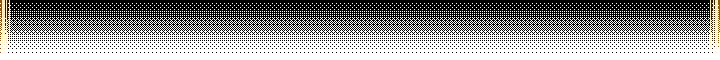「さあ……本当に何を視たんだい?」
落ち着いて言ってごらんと、サウルは促した。
混乱から立ち直った“真白の闇姫”連理は、一瞬の間に脳裏を駆け巡った予知を整理して、少しずつ語り始めた。
「戦いが見えたのじゃ。だが、何が戦っておったのかはわからぬ」
「それは、戦争のような戦いだった?」
「違うのう。対立する二つの何者かの闘いじゃ」
「では、何故、それが誰なのかわからないんだい?」
「何か……水のような膜を通して見ておるかのように、ぼんやりと姿がゆらめいておったからじゃ。影のようでもあったの。そして速かった。どちらも、暴れまわっているかのようじゃった」
連理は視えた物の細部を思い出そうとして……頭を振った。
「ここと同じ世界ではないのかもしれぬ。その2体は、アルメイスの街並みの上に被さるように見えておった。じゃが、街並みが壊れていたわけではない……視えたままの大きさであれば、恐ろしく巨大じゃ……リエラじゃろうか」
「どのような形だった……?」
「片方は……龍のようじゃった。片方は、形が更に鮮明ではなかった。人型じゃとは思うがのう」
幻のような闘いだった。現実感の薄い予知。
「……それが何故、君をあんなにも混乱させたんだろう?」
サウルは誘導するように問いを続ける。
「……恐ろしかったからじゃ。理屈ではないの」
「恐ろしかった?」
「そうじゃ。アルメイスが破壊されていたわけではないぞ。じゃがの……」
アルメイスが窒息していくような気がした。
ゆるゆると。
「他には?」
見えすぎたと、連理は予知の際に言った。
では他に視えた物はなかったかと、サウルは問う。
「あったと思う。じゃが、もう思い出せぬ。一瞬の間に……見えすぎたのじゃ」
ああ……と、連理は考え込んだ末に、一つだけ思い出したと言った。
「雨が降っておった……」
「雨?」
「そうじゃ、アルメイスの街に」
サウルは、自ら双樹会と学園長に宛てて手紙をしたためると言った。何が起こるかはわからないが、何か起こるかもしれないことを隠すこともないと。不思議な予知の話は、知る人ぞ知るところとなるようだった。
「君の見たそれは、ラウラ・ア・イスファルに関わる未来の一つなんだろうね」
そう言って。
だが、予知の時は、何事もなく通り過ぎていった。
元々、さほど先の未来ではなかったはずだった。
当たったのか、当たらなかったのか、それはわからない。
だが、アルメイスの上空に怪しい影が現れることはなかった。
見えなかったのかもしれない。
ただ……
雨は降った。
かねてよりアルメイスを覆っていた厚い重い雲から、雨が降り始めた。
耐えかねたように降り出した雨は、しばらく降ってはやみ。やんでは降って。
徐々にその時間を長くしていくようだった。
それが今年の初雪に変わったのは、いつであったか。
雪は、アルメイスに降り積もっていく。
静かに……
アルメイスをやさしく絞め殺すかのように。
幼い少女は、まだ声の主を探していた。
今は雪の降る空を見上げる。そして街を見回す。
「どこ……?」
戸惑うような呟きが、その唇から漏れる。
「どこにいるの……?」
見えていたものを、見失ったかのように。
それでも少女は探し続ける。
それは、ラウラ・ア・イスファル――ではない。
それは、純粋なる声の源。
それは、純粋なる魂の声。
それは……
その悲しみを慰めるために。
赤毛の少女は、まだ秘密の場所を探していた。
ラウラ・ア・イスファル。それは、力を与えてくれる場所。伝説ですらない、約束の場所。
それでも、強い意志をもって、彼女はラウラ・ア・イスファルを探していた。
彼女と共にいた者は、遠からず悟っただろう。彼女は、声の主を探しているのではないことを。
ただ、純粋なる力を。
ただ、純粋なる未来を。
ただ……
自分の弱さを脱ぎ捨てんがために。
「ラウラ・ア・イスファルはどこなのだ!?」
もちろん、ランカークもまたラウラ・ア・イスファルを探し続けていた。
幾らかの協力者を得て、あちこちを手広く探している。ランカークにとって最大の幸運は、フランの参加だろうか。
フランは最近、酷く眠たがるようになって、積極的に……という参加ではなかったが、体調の良いときには調べ物を中心に協力していた。
彼らは探し続ける……彼らの望むものを。
手がかりは、かつて噂に語られた場所。
手がかりは、目撃談が減少しつつある……彼の幽霊。
雪は降り始めた。
砂時計の砂が落ちるように。
最後の一粒へ向けて……時は流れ始めたのかもしれない。
雪は降り続ける。
「いつまで降り続けるつもりかしら」
学園長は報告書に目を通すと、そうコメントした。マイヤは、それに静かに答える。
「例年よりも初雪は早く、また降雪量は増加の傾向にあります。今年はじきに雪かきと雪下ろしが必要になりましょう」
「雪かきと雪下ろし……ね。言葉だけなら、のどかだわ」
「今のところ対症療法以外に、方法があるわけではありませんので……早い対策は必要かと」
「そうね。中心街路は人を雇って、早めに対応して。住人にも今年は早めに雪害対策を始めるように注意を呼びかけてちょうだい」
少し考えた後……学園長は付け足した。
「それと……雪は食べないように、と」
「は……しかし、水を飲まないわけにはいきませんが」
「わかってるわ。気休め程度よ。でもね」
その後は続けず、学園長は学生会長を見つめた。
「御心のままに。殿下」
――マイヤに、否と言う権利はない。
「……殿下、もしも、ラウラ・ア・イスファルの真実に触れる者が現れたときには……どうなさいますか?」
マイヤの問いに、学園長は心配要らないと首を振った。
「たどり着けはしないでしょう。仮にたどり着けても、それは所詮ラウラ・ア・イスファルの過去の幻」
そのとき、どう答えるべきかは決まっていると。
「新たなラウラ・ア・イスファルに、気付く者はいないわ」
それは誰も知らない……レアン・クルセアードさえも、と。
知っているのは……
「私と、あなたと……エリスだけよ」
ほどなく学生たちと街の住人のすべてに布告されたものは、二つ。
屋根の雪下ろしと、道の雪かきの奨励。
それから……
「雪を食べてはいけない」という不思議な禁止令だった。
雪は降る。
降り積もる…… |
|