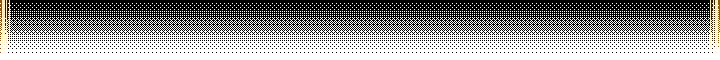「よんでる」
少女は空を見上げて言った。
今にも泣き出しそうな曇天を。
「よんでるよ、おとうさん」
どこから聞こえてくるのか、少女にわかっていたはずはない。むろん、空から聞こえていたわけでもない。
「そうか……ラジェには聞こえるんだね、あれが」
「うん。おとうさんにもきこえる?」
「聞こえるよ……深い深い交信だね。世界のすべてに囁くような……どうしたんだろうね……」
「いかないの? おとうさん」
「……行きたいかい? ラジェは」
少女は遠い重い空を見上げる。
「だって、かわいそう……」
「フラウニー! フラウニー!!」
けたたましい羽ばたきが、薄暮を揺らす。
放課後の学課棟。その廊下のことだった。
薄暗いのは、空が曇っているからだ。今にも降り出しそうな空。まだ雪には早い。降るならば雨だ。
ぼんやりとフランは歩いていた。
「フラウニー!」
何も聞こえてはいないかのように。足取りは、どこかよろよろとしていた。
「フラウニー!!」
イルズマリの声にも焦りの色が濃くなってくる。
だが、イルズマリはフランを呼びとめはしたが、何故とは問わなかった。この理由は知っていたのかもしれない。
フランの顔は、どこか苦痛に歪みはじめていた。行きたくないのに、どこかに向かおうとしている……背反した葛藤があるかのように。
そのままフランが外に出ようとした時のことだ。すらりとした人影が、その前に立った。
音もなくしなやかに。
そして。
ぱんっ!
小気味の良い音がした。
「……エリスさん?」
フランには一瞬、どうしてエリスが前に立っているのかも、どうして自分の頬が痛いのかすらもわからなかったようだが……
「私……」
「……殴ったのは、悪かったわ」
ただそれだけ言って、エリスは踵を返す。
フランは、まだしばらく呆然とそこに立っていた。
その後、フランとエリスが喧嘩したという噂も流れたが……どちらもそれについてあまり語りたがることはなかった。
その日、その声ならぬ声が聞こえたという者はアルメイスの学生の一割にのぼったという。それは年齢にも性別にも、また成績や血筋にも偏るものではなかったらしい。何か法則はあるのかもしれなかったが、誰もそれは知らなかった。
それは、直接聞こえたという者も、交信だったという者もいた。
呼び声だったと言う者も、呪詛の言葉だったと言う者も、意味を成さぬ言葉だったと言う者もいた。
女の声だったと言う者も、男の声だったと言う者もいた。
それらの証言からは、何一つ特定することはできなかった。
呼ばれたと言う者も、どこへ呼ばれたのかわからない。
ただ……いつしか噂が流れていた。
「あれはラウラ・ア・イスファルからの呼び声だ」と。
「人が人でなくなる魂の根源からの呼びかけだ」と。
あれに応えられる者は、フューリアとしての更なる力を得るのだと。
あの声が呼んでいた場所へ、たどり着けた者は……
「ねぇ、カレン。あれ……聞こえた?」
修練場での訓練の合間に、そう聞いて回っていたのはクレアだ。今はカレンに聞いているが、誰にも同じようなことを聞いていた。
「全然」
カレンはあっさり首を横に振る。
「そっかー」
「どうしたの?」
「んー……」
少し離れたところにいるルーをちらりと見て、クレアはそっと言った。
「呼ばれた場所に……ラウラ・ア・イスファルに行ければ、力が手に入るって噂じゃない?」
「それって……噂でしょ?」
「そーなんだけどさー」
にゃははーとクレアは誤魔化すように笑った。
ラウラ・ア・イスファルがどこであるかについては、様々な噂が流れていた。
それはたとえば、図書館にある秘密の扉から繋がった異世界であると。
あるいは、研究所群の中に誰も知らない建物があると。
修練場の結界の隙間が、その入口であると。
微風通りの秘密の小路が、そこであると。
だがまだ誰も真実は知らない。
「ラウラ・ア・イスファル探索だ!」
……言い出すと思った、と従者は内心で頭を抱えた。もちろん表にはおくびにも出していない。
今、叫んだのはランカークである。
彼女は自分の主がとことん強欲であることを知っていたので、今回も何かするのではないかとは思っていた……が。実にストレートに、噂に踊らされているような気がした。
「ラウラ・ア・イスファルを探し、その力を手に入れるのだ!」
どうやって、とか、そういうことはランカークは何も考えていないだろう。
「更なる力……私にこそ相応しいと思わんか!?」
「――仰せの通りで」
コメントは差し控えたい気分ではあったが、ここで受け流せずにはランカークの従者は務まらない。ただ、これからあてもない捜索が始まるのかと思えば、気が重かったが……
「なんか、忙しそうだね」
そのとき、この屋敷の居候であるサウルが扉のところから声をかけてきた。
「ああ、いえ、それほどのことでは……何かご用で?」
へこへこと、ランカーク自身がそう答える。
「うん、長いことお世話になったけど、そろそろ家を借りて引っ越そうと思うんだよ」
「そんな、ご遠慮なさらずとも」
ランカークは慌てるようにそう言ったが……サウルは、もう引越しは決めているようだ。
「ううん、ずっと考えてはいたしね。物件は見つけたんだが……長いことお邪魔してたから、荷物も増えちゃったしね。引越しの手を借りたいんだけど、彼女をちょっと貸してもらえるかい?」
「それぐらいでしたら、いくらでも。……さあ行って、お手伝いしてくるんだ」
ランカークは従者を、サウルのほうへ追い立てた。
「ありがとう、邪魔してごめんよ。実際に荷物を運ぶときには、もう少し人手が要るかなぁ」
そこで従者はサウルの後について、部屋を出た。とりあえず、当面は『ラウラ・ア・イスファル探索』から解放されたらしい……執行猶予がついただけだが。
ランカークはそう簡単には諦めないだろうから、彼女が他の仕事をしている間も、他に人を集めて探すだろう。
「そういえば」
そんな彼女の考えを見透かしたかのように、彼女の前を歩くサウルは言った。
「ラウラ・ア・イスファルって場所を意味する言葉じゃないと思うんだけど、どうしてあんな噂になってるんだろうね?」
少しの絶望と、少しの切なさと、少しの希望に、彼女はぎゅっと眉間に皺を刻んだ。 |
|