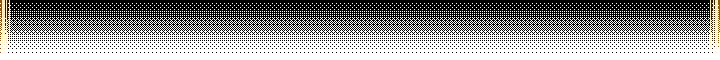「いいか、くれぐれも粗相があってはならん!」
学園都市アルメイスにおいて上流階級の子弟で作られた集い『貴族連合』の長であるアドリアン・ランカークは、彼の従者に唾を飛ばしつつ、くれぐれもと繰り返していた。
それが何度目であるか従者は律儀に数えていたが、それを主人に言い述べるようなことはしない。そんなことをすれば、ただでさえ興奮気味の主人は癇癪を起こすかもしれなかったからだ。
「危険のないよう、陰ながらお守りするのだぞ。私も、あの方がこのアルメイスにいる間は、出来る限りご一緒する」
あの方というのが実際に誰であるのか、ランカークは言葉を濁しているので、従者にはよくわからなかったが、とにかくエライ人であるようだ。わかっているのはそれと、帝都から来るということだった。
「後は、茶会の支度だ。招待状は発送したか?」
「はい、名簿の通りに」
「先方のご希望だからな。『学園に所属する、高貴なる茶会に相応しき者』を招待し、学園の中庭を使って、盛大なガーデンパーティーだ。そちらの準備も滞りなく行わねばならん」
そのとき、時計塔の鐘が聞こえた。
「おお! もう時間だ! 駅に向かうぞ」
ばたばたとランカークは部屋を出て行く。その後を、音もなく従者はついていった。
「…………」
「お父上からの手紙に、なにが書かれていたのであるかね? 浮かない顔をしておるが」
イルズマリ……イルが肩に舞い降りると、フランは手紙を閉じた。
「アルメイスにお客様がいらっしゃると」
「フラウニーに会いにであるか」
「いいえ、そういうわけではないんですけど。お父様がわざわざお知らせくださるというのは」
アルメイスは帝国にとって重要な施設である。政府高官がたびたびこっそり視察に来るということも、常々噂されているところだ。フランの手にある手紙に書かれていることも、その噂されるような出来事の一つであるとも言えたが。
今までに、フランは父から事前にそんな客人がアルメイスを訪れることを知らせる手紙を受け取ったことはなかった。これは、いつにない、珍しいことだった。
「そうである、フラウニー、もう一通手紙が来ている」
イルはサイドテーブルの上を示した。そこまでイルが運んできて、それからフランの肩に乗ったらしい。
「もう一通?」
手に取ると、貴族趣味な豪奢な透かしの入った封筒だ。封を切るとふわりと良い香りがした。
「アルメイスを視察にいらっしゃった貴人をおもてなしする、お茶会……」
差出人はアドリアン・ランカークだ。フランは悪い人ではないと思っているが……ランカークの回りの評価も知ってはいる。
しかし、茶会。これほどに大々的に、大っぴらに、視察をしていった高官が、過去にはいただろうか。理由を問われたなら答えられない、そこはかとない不安が、フランの心に影を射していた。
「出席しますかな? フラウニー」
「ええ。御招待をお断りする理由はありませんから……」
「……何? これは」
「招待状のようです」
学園長は白い封筒の封を切って、眉をしかめた。すかさずその問いに、横にいた双樹会会長、マイヤが答える。
「そういえば、茶会の会場に中庭を使う許可を求める書類は出ていたわね」
「ずいぶんたくさんの者に招待状を出したようです。僕のところにもまいりました」
視察に来た貴人の歓迎のために催される茶会。だがその肝心のところの、歓迎する主賓は誰なのかは、ぼかして書かれていた。もちろん、学園長は訪れる者の名を知らないわけはないのだが。招待状の文面は生徒たちに配られたものと、同じなのだろう。
「そう。欠席の連絡をしておいて」
「よろしいので?」
「あなたが行くのなら、それで問題はないでしょう」
淡々と、学園長は次の書類を手に取る。
「御心のままに」
マイヤは、深く頭を垂れた。
「招待状、来た?」
「ううん、来てない」
「あの人のところには、来たんですって」
すでに、そんな囁き声がアルメイスのあちこちで聞こえる。
「私には縁がない話ね」
研究所の買出しのために微風通りを歩きながら、マリーが呟く。そう思ったところで、足元に封筒が、絡まった。風に運ばれてきたようだ。
前を見れば、ルピニアン劇場からの出張か、ビラ配りをしている赤い髪の少女と黒髪の少女がいる。名前くらいは知っている相手だった。クレアとルーだ。
「これ、クレアの?」
「へ? ううん〜あたしのじゃないよぉ」
もらってないもん、とクレアは首を振る。
汚れてはいるが、これが噂の招待状であることはすぐにわかった。噂の足は早いので、封筒がどんなだかくらいは、アルメイスの学生ならばほとんどが知っているだろう。
「ルーの?」
「……いいえ……招待されてませんから……」
招待されても、行かないけれど……とルーは俯きがちに呟くように言う。
クレアはマリーと一緒に首をかしげて、考え込んだ。
「通りを歩いてった人のかも」
「宛名、読めなくなっちゃってるわね」
マリーは目の上に封筒をかざしているが、汚れて宛名は見えなくなってしまっていた。
「落とした人、困ってるかな」
「うーん、じゃあ、探してあげよ!」
クレアがにぱっと笑って、そう言うが……
「私、買い物の途中なんだけど」
「えー、ダメ?」
「…………」
「…………」
「……わかったわ、乗りかかった船だし。失くして困ってるなら、聞いていけばすぐわかるでしょ」
ふう、とマリーは息を吐く。
「そーだよ! 探すの手伝ってくれる人もいるかもしんないしね!」
もちろん自分たちも手伝う、とクレアは言う。ビラを配りながらだが。
マリーはなんとなく貧乏くじを引いた気分になりながらも、道行く人に声をかけ始めた。
「ようこそいらっしゃいました」
揉み手せんばかりの態度で、ランカークは駅で列車を降りた客人を迎えた。
「出迎え、ご苦労様」
黒髪の、黒衣の青年は人当たりの良さそうな笑みを浮かべ、ランカークをねぎらう。
「普通の列車でいらしたんですね」
「特別列車を仕立てたりはしないよ、お忍びだからね」
「そうですよね! もちろん」
ランカークにエスコートされ、駅の前に停められていた馬車に乗り込む。このまま、アルメイス一の高級ホテルに向かうのだ。
馬車の中で腰を降ろしたところで、黒衣の青年はランカークに訊ねた。
「ところで……」
「なんでしょう、サウル様」
「頼んでおいたことはしておいてくれたかな」
「はい! 招待状は出し終えております。ここに名簿も」
ランカークから渡された名簿に軽く目を通し、ふむ、と黒衣の青年、サウルは息をついた。
「この名簿には、彼女たちの名前がないな」
「ええ!? どなたが漏れてしまったのでしょう」
招待客の選別は完璧に行ったつもりだったのに……と、ランカークは緊張のせいかわなわなと震えている。
「ええと、クレアと言ったかな、あの赤毛の娘は。後、その子と一緒にいる、ルチアルって娘だ」
「クレアとルチアル……」
「必ず、彼女たちも連れてきておくれ」
「わかりました! これから招待状を送りましょう。この招待を断ることはありますまい」
「必ずだよ、いいね」
はいっ、とサウルの言葉にランカークはかしこまる。
「それから……警備の人手は惜しまないように。レアンと言う不心得者がアルメイスを騒がしていると聞いているよ」
「はっ」
自分の屋敷に帰り、ランカークはうろうろと部屋を歩いていた。
「人手か。ええと、手隙の学生に命じて……」
頭を悩ませているのは、サウルの身の回りや茶会の警備の増強の問題だ。
それから、クレアとルーが出席を拒んだ際に、どうするか。
「おい!」
「なんでしょうか」
影のように控えていた従者は、呼ばれて、一歩前に出た。
「クレアとルーという娘が招待を断った場合は、さらってでも連れて来るんだ。なに、茶を飲むだけだ、怪我をさせようというわけじゃないからな」
「わかりました」
従者は微かに眉根を寄せ、目を伏せた。 |
|